こんにちは、2級ファイナンシャルプランニング技能士のオットです。
個人事業主として仕事をしていると、プライベートと事業の両方に関係する生活費があります。
例えば、自宅の家賃や電気代、スマホの料金など…
こういった支出は、事業に使った分だけ経費として計上する「家事按分(かじあんぶん)」を使うことで、経費として処理することができます。
今回は、家事按分の基礎知識から、実際の按分例、注意点までわかりやすく解説していきます。
節税を正しく行うためにも、ぜひチェックしてみてください!
家事按分とは?
家事按分とは、私的支出と事業用支出が混在している支出について、事業で使用した割合だけを経費として計上する方法のことです。
たとえば、自宅を仕事場として使っている人は、家賃や光熱費などもプライベートと共用しているはずです。これらの支出は、事業で使ったと説明できる分だけ経費にしてOKというルールになっています。
家事按分が可能な費用とは?
代表的なものを以下にまとめました。
- 家賃
- 電気・水道・ガス代
- 通信費(スマホ・Wi-Fiなど)
- 自動車関連費用(ガソリン代・保険など)
- サブスク系のサービス(音楽配信・ソフト利用料など)
具体的な按分割合は後述するのでご覧ください。
雑所得でも家事按分は可能!
家事按分は、事業所得の個人事業主だけができる節税法ではありません。
実は、雑所得で申告している場合でも家事按分は可能です。
事業所得と雑所得の違いがまだよくわからないという方は以下の記事をご覧ください!
例えば、副業でブログや動画制作、イラスト制作などをしている人が「雑所得」で申告している場合でも、事業に使っているスマホ代や自宅の家賃、光熱費の一部を経費にできます。
ただし、注意点としては「事業としての実態があること」が必要です。
「何となく使った」「一度だけの副業収入」といった曖昧なケースでは認められないこともあるため、使用実態と支出の記録を残すことが大切です。
費用ごとの按分の考え方と具体例
家賃
自宅の一部を仕事場として使っている場合、そのスペースの割合に応じて家賃を按分します。
📌 例:自宅の床面積が50㎡、そのうち10㎡を仕事に使っている → 家賃の20%を経費に計上
🔍 ポイント:面積+使用時間も加味できるとより現実的な割合になります。
電気・水道代などの光熱費
電気代や水道代も、仕事で使った分だけ経費にできます。
仕事用スペースの電力使用割合や、仕事時間の割合を参考にして按分するのが一般的です。
📌 例:電気や水道を稼働させる時間 → 毎日16時間
平日8時間程度を仕事に使用(全体の約33%)→ 光熱費の1/3を経費に
💡 エアコンの稼働時間や在宅ワークの時間を基にした算出も有効です。
【補足】按分割合が曖昧な場合
光熱費などで「業務でどのくらい使っているかの比率が曖昧」なときは、家賃の按分割合に合わせて計上するという方法もあります。
例えば、家賃を全体の20%で按分しているなら、光熱費も同様に20%で経費計上するという考え方です。
この方法は実務でもよく使われており、特に面積や使用時間で判断しにくい支出には有効です。
通信費(スマホ・Wi-Fi)
スマホやインターネットは、私用と仕事の境界が曖昧になりがちな支出の代表格です。
こちらも使用時間や用途に基づいて按分します。
📌 例:スマホ等を利用する時間の半分ほどは仕事に利用 → 月額料金のうち50%を経費に
自動車関連費用
自家用車を仕事にも使っている場合、走行距離や使用日数に基づいて按分可能です。
家事按分の対象は、ガソリン代に限らず、自動車保険、自動車税及び車検費用等も含まれます。
📌 例:仕事での使用が全体の30% → ガソリン代や保険料等の30%を経費に
サブスク・アプリ系サービス
YouTubeプレミアム、Spotify、Adobe、Canvaなど、業務でも使っているサービスは按分対象になります。
📌 例:動画編集の仕事にYouTubeを参考として視聴 → 利用時間のうち20%を業務使用と判断 → 20%を経費計上
家事按分で気をつけたいこと
- 按分の根拠を説明できるようにする
→ 「面積」「時間」「使用日数」など、合理的な説明が必要です。 - 按分比率は一度決めたら、できるだけ継続して使うこと
→ 年ごとに大きく変えると、税務署から説明を求められることも。
※ 按分比率を本来より低くすること(経費を少なくすること)は、納める税金が多くなるだけなので、特に問題視されない。 - 記録を残しておく
→ 領収書だけでなく、按分の理由や計算式などもメモしておくと安心です。
【参考】家事按分するとどれくらい違うのか節税効果を検証
家事按分をする場合としない場合で、どれくらい納める税金と手残りが変わるのか、簡単に検証してみます。ぜひ参考にしてみてください。
家事按分対象費用の例
家事按分の対象になる生活費が以下の通りだったとします。
| 項目 | 金額(年間費用) |
|---|---|
| 家賃 | ¥1,200,000 (100,000/月) |
| 水道光熱費 | ¥360,000 (30,000/月) |
| 通信費(スマホ+ネット環境) | ¥96,000 (8,000/月) |
| 自動車関連(ガソリン代、自動車税、保険、車検など) | ¥132,000 (ガソリン代 6,000/月) |
家事按分割合の例
家事按分の割合は以下の通りだったとします。
| 費用の種類 | 家事按分割合 |
|---|---|
| 家賃 | 30% |
| 光熱費 | 30% |
| 通信費 | 50% |
| 自動車関連費用 | 50% |
※ あくまで例です。ご自身の実態に基づいて判断しましょう!
家事按分を行なった場合の節税効果を検証
上記家事按分割合に基づいて、生活費の一部を家事按分した場合としなかった場合で、その節税効果を所得税を参考に確認してみましょう。
| 項目 | 家事按分なし | 家事按分あり |
|---|---|---|
| 収入 | ¥5,000,000 | ¥5,000,000 |
| 家賃 | ¥0 | ¥360,000 |
| 水道光熱費 | ¥0 | ¥108,000 |
| 通信費(スマホ+ネット環境) | ¥0 | ¥48,000 |
| 自動車関連(ガソリン代、自動車税、保険、車検など) | ¥0 | ¥66,000 |
| 家事按分以外経費 | ¥800,000 | ¥800,000 |
| iDeCo | ¥816,000 | ¥816,000 |
| 所得控除(基礎控除のみ) | ¥480,000 | ¥480,000 |
| 青色申告特別控除 | ¥650,000 | ¥650,000 |
| 課税所得 | ¥2,254,000 | ¥1,672,000 |
| 所得税 | ¥127,900 | ¥83,600 |
| 税引後の収入 | ¥3,256,100 | ¥2,802,000 |
| 手残り(税引後収入 – 残りの家事按分費用) | ¥1,468,100 | ¥1,596,000 |
あくまで一例ですが、家事按分を行わずに所得税引後の手残りから家賃等の生活費を全額支払った場合、手残りは146.81万円になるのに対し、一部家事按分すると、手残りは159.6万円になります。つまり、家事按分を行い生活費の一部を経費にすることで、納めるべき税金が少なくなり、手元に残るお金も多くなります。
収入、所得控除、課税所得などの言葉の意味や関係性がまだよくわからないという方はぜひ以下の記事もご覧ください。
また、青色申告について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
家事按分の制度については、適切な範囲内で最大限活用しない手はありません。事業所得でも雑所得でも実施可能なので、ぜひ上手に活用しましょう。
まとめ
✔ 家事按分とは、事業とプライベートが混在する支出を“事業に使った分だけ”経費にできる制度
✔ 対象となるのは、家賃・光熱費・通信費・自動車費用・サブスクなど幅広い支出
✔ 按分の基準は「使用面積」「時間」「目的」など、合理的に説明できる根拠を用意することが大切
✔ 事業所得に限らず、雑所得の副業でも按分は可能。副業者にもおすすめの節税方法!
✔ 計算方法や理由をメモとして残しておけば、税務調査が来ても安心!
家事按分を上手に取り入れることで、本来なら支払わずに済む税金をしっかり節約できます。
自宅や日常の支出の中にも“経費にできる部分”は意外と多く存在します。
「この支出、仕事でも使ってるけど…」と思ったら、一度立ち止まって按分できるかを考えてみましょう。
正しく理解し、実態に即した処理をすれば、あなたの手元に残るお金はもっと増やせます。
このブログでは、お金の基礎知識・投資・個人事業に関する情報を発信しています。
今後も皆さんの参考になる情報をお届けしていきますので、ぜひチェックしてください!
ではでは。。。



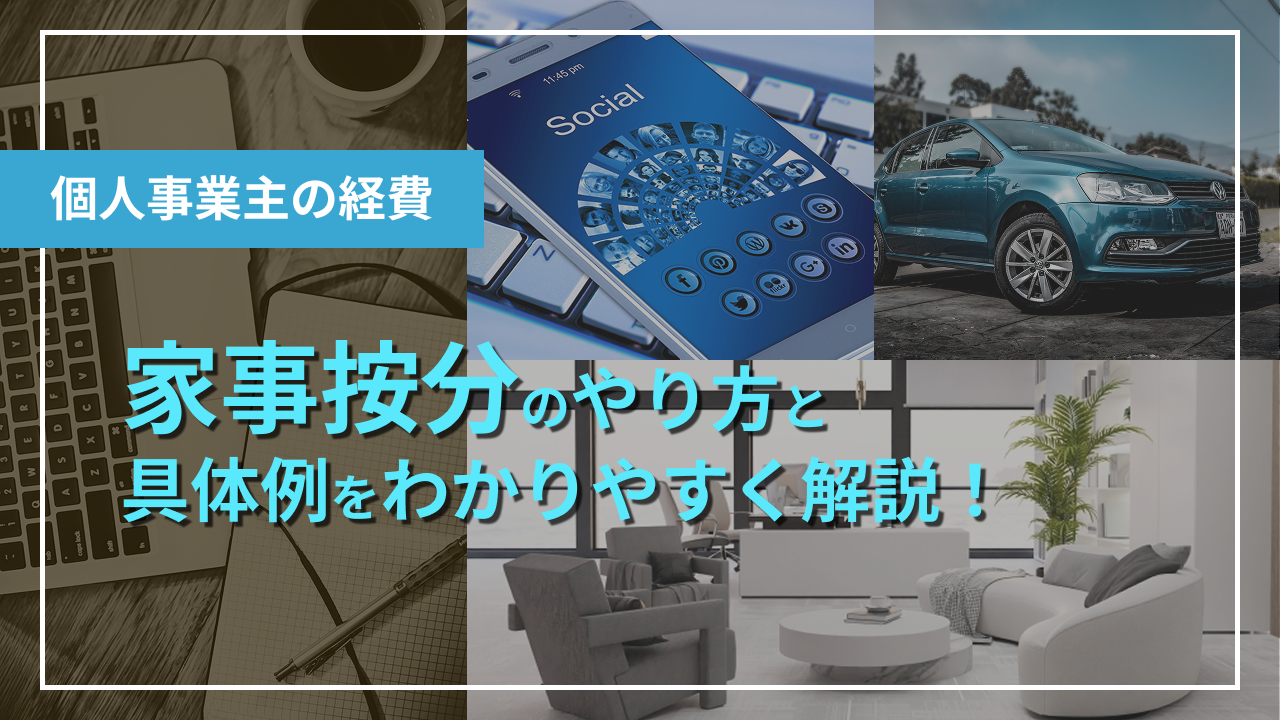

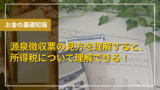



コメント